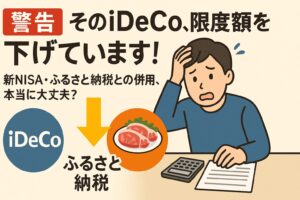目 次
【結論】新NISAとiDeCo、相続の扱いは全くの別物です!
最初に、この記事の最も重要な結論からお伝えします。新NISAとiDeCoでは、亡くなった後の資産の扱われ方が根本的に異なります。下の比較表で、その違いを一目で確認してください。
| 項目 | 新NISA | iDeCo(死亡一時金) |
|---|---|---|
| 資産の扱い | 相続財産 | みなし相続財産 (受取人固有の財産) |
| 対象となる税金 | 相続税 | 相続税 (※優遇あり) |
| 非課税枠の有無 | なし | あり (生命保険金と合算) 500万円 × 法定相続人の数 |
| 受取人 | 法定相続人 | 指定した受取人 (最優先) |
| 遺産分割協議 | 対象になる | 対象にならない |
モバイル端末では、横にスクロールして全体をご確認いただけます。
【新NISAの相続】手続きと「非課税メリット終了」の注意点
新NISA口座の資産は、預貯金や不動産と同じように、シンプルな「相続財産」として扱われます。
手続きは比較的わかりやすいですが、一つだけ非常に重要な注意点があります。
注意点:非課税のメリットは引き継げない
新NISAの最大のメリットである「非課税」は、口座名義人本人にのみ適用されます。
そのため、名義人が亡くなった時点でNISA口座は廃止され、保有していた金融商品は相続人の「課税口座」に移管されます。
つまり、相続した後に利益が出た場合は、通常通り約20%の税金がかかることになります。
手続きは、以下の流れで進めるのが一般的です。
図解で全体の流れを掴みましょう。
-
金融機関へ死亡の連絡
-
相続手続きの書類を取り寄せる
-
戸籍謄本・遺産分割協議書などを準備
-
書類一式を金融機関へ提出
-
相続人の「課税口座」へ資産が移管
相続税については、他の財産と合算して基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税対象となります。
【iDeCoの相続】税金で損しないための最重要知識
iDeCoは、新NISAと比べてルールが複雑ですが、その分、知っていれば大きな節税効果が期待できる制度です。
絶対に押さえておきたい3つのポイントを、グラフや図解を交えて解説します。
ポイント①:「受取人指定」が何よりも最優先される
iDeCoの死亡一時金は、遺言書よりも事前に指定した「受取人」が最優先で受け取ります。
これは、受取人固有の財産とみなされるため、面倒な遺産分割協議の対象にもなりません。
まだ指定していない方は、今すぐにでもiDeCoの加入者サイトで設定・確認しましょう。
これが最も簡単で、最も効果的な相続対策です。
ポイント②:生命保険金の「非課税枠」が使える!
iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」として、生命保険金と同じ枠で扱われます。
これにより、「500万円 × 法定相続人の数」という非常に大きな非課税枠を利用できます。
下のグラフを見れば、その効果は一目瞭然です。
iDeCo死亡一時金の非課税枠は相続人の数で増える!
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税になります。
これは相続税を計算する上で絶大なメリットです。
ポイント③:受取人で「かかる税金」が変わる
iDeCoの死亡一時金は、誰が受け取るかによってかかる税金の種類が変わり、税負担が大きく異なる可能性があります。
この複雑なルールを、下の図解でスッキリ理解しましょう。
このように、法定相続人(配偶者、子、親など)を受取人に指定しておくことが、節税の観点から最も有利と言えます。
【2025年最新】今日からできる!家族のための相続対策アクションプラン
知識は行動してこそ意味があります。
今日から始められる、たった3つのシンプルなアクションで、未来の家族の負担を劇的に減らすことができます。
ぜひ、できることから実践してみてください。
【STEP1:最重要】iDeCoの受取人を「指名」する
これはこの記事で最も簡単かつ効果絶大なアクションです。
受取人を指定しておくだけで、あなたの意思通りに、面倒な手続きをすっ飛ばして資産を大切な人に渡せます。
これは、未来の家族へ送る「最後のラブレター」のようなもの。
今すぐ、iDeCoの加入者サイト(楽天証券、SBI証券など)にログインして確認・設定しましょう。
【STEP2:家族への道標】資産の「ありか」を記す
もしもの時、家族はあなたの資産の全体像を知りません。
「どの証券会社?」「IDは?」と、まるで暗号解読のように探し回ることになってしまいます。
その負担をなくすため、エンディングノートや安全な場所に保管するメモに、以下の情報を残しておきましょう。
- 金融機関名:(例:〇〇証券、△△銀行)
- 口座の種類:(例:新NISA、iDeCo、特定口座)
- ログインIDやお客様番号など:※パスワードは別に保管するのが安全です
- 担当者や連絡先:(もしあれば)
これだけで、残された家族の手続きは驚くほどスムーズになります。
【STEP3:上級編】元気なうちに想いを渡す「生前贈与」
相続税が心配になるほど資産がある方は、元気なうちに資産を贈与する「生前贈与」も非常に有効な手段です。
年間110万円の非課税枠を活用することで、将来の相続税を計画的に減らすことができます。
【要注意】2024年の制度改正
亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールに変更されました。
つまり、「まだ早い」と思わずに、早めに計画を立てることがこれまで以上に重要になっています。
一度、税理士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
まとめ:未来の家族への最高の思いやりは、今のあなたの準備から
この記事でお伝えした重要なポイントを、最後にまとめます。
✅ iDeCoは「死亡一時金の受取人指定」が何よりも重要で、最大の節税対策になる。
✅ iDeCoは生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えて、相続税上有利。
✅ 今すぐiDeCoの受取人を確認し、家族と資産情報を共有することが、最高の相続対策。
相続の手続きは、あなた自身がすることはできません。
だからこそ、元気なうちに正しい知識を身につけ、準備をしておくことが、未来の家族への最高の思いやりとなります。
まずは第一歩として、iDeCoの加入者サイトを開いて、受取人を確認することから始めてみませんか?